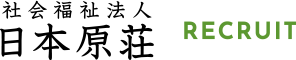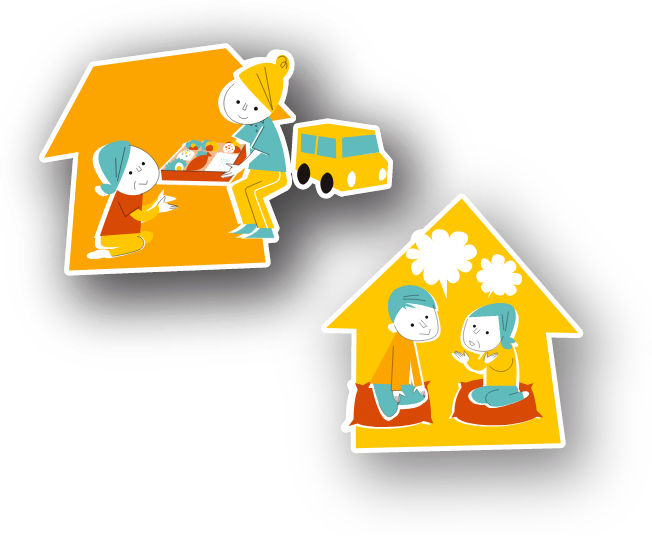
スローガン
社会福祉法人日本原荘は、社会課題に対して正面から向き合い、
質の高い介護サービスの提供、地域づくりを通じて
持続可能な地域社会の実現に貢献します。

日本原荘は昭和41年に設立し、翌年には中国地方初となる特別養護老人ホームを開設しました。設立当初から地域や行政とのつながりを大切にしながら、地域社会や福祉サービスの課題に積極的に向き合い、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けていけるようサポートしてきました。現在では特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、デイサービス、ショートステイなど18事業所の運営をしています。
よりよい地域であることは、地域で良質なサービスを提供するための前提条件です。地域が持続できない状態になってしまうと、福祉サービスの継続は難しくなってしまいます。
私たちは、この地域で安心して生活するためにも、持続可能な社会の実現を目指すSDGsへの取り組みが必要だと考えます。SDGsは行政や大企業のみが取り組む目標ではなく、ひとりひとりが取り組むべき目標です。私たちが行っている地域が豊かになるような取り組みが推進されることで、福祉も推進されるプラスの環境をつくることを目標にし、SDGSを推進してまいります。
⽣活⽀援サポーター養成事業
高齢者が住み慣れた地域で自分らしく生活できるよう、一般の方を対象に、ボランティア養成を展開しています。座学と実践を終えたあとは実際に高齢者世帯へ行って、外出支援・そうじ・ゴミ出し、また話し相手になっていただきます。津山市と一緒に行なっています。
(サポーター登録者数は今までで50人!)

配⾷サービス
料理することが困難で、栄養状況の悪化が懸念される高齢者世帯に平日の昼食を低額負担でお届けしています。配達されるお弁当は管理栄養士監修のもと、栄養バランスばっちりです。日本原荘の職員が直接配達するので、見守り安否確認もあわせて実施しています。

勝北つどいの場「福ちゃん家」
「福ちゃん家」は、普段ひとりで自宅にいる高齢者が集まって、お茶やおしゃべりを楽しむためのコミュニティです。
交流の場を提供し、地域に孤立させないことを目的として事業を行っています。先程紹介した生活支援サポーターにも運営として協力いただいています。
(これまで1000名近くの方が参加されています!)
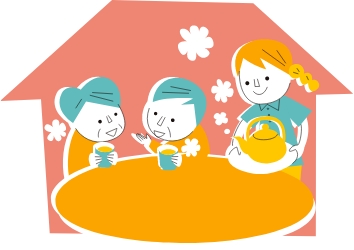


中学校等の福祉教育活動に
おける職員派遣
地域の中学校、看護専門学校などへの出張授業を通して、生徒に福祉の現状や人のつながりの大切さを伝えています。まずは座学で高齢者との関わり方や日本原荘がどんな施設なのかを学びます。そのあとは車椅子の使い方などを実践で学び、実際に日本原荘に来て利用者さんと関わっていただきます。



その他の活動
- 災害時における各種支援活動の実施
- 生活困窮者就労訓練事業
(生活困窮者自立支援制度) - 生活困窮者支援活動
- 障がい者の中間的就労支援